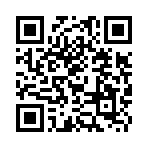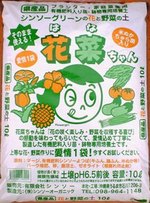2009年02月18日
オニヒトデを有機肥料の原料として有効活用を目指す!
本日18日(水)に弊社代表の與那嶺がFMよみたん(78.6MHz)午後2時からの番組『第7よみたん丸』の『海を守るプロジェクト』コーナーにゲスト出演します
主な内容は、『サンゴを守る活動において駆除した後のオニヒトデを有機肥料の原料として有効活用を目指す』という内容でお話します。
弊社は、2年ほど前からこのオニヒトデについて有効利用できないか検討・準備を進めており、昨年、読谷村漁業協同組合と協力の依頼をしていました。
今回、その考えや取り組み方をラジオで話して欲しいと依頼になり、ゲスト出演する事になりました。
昨年、八重山地域でオニヒトデが大発生し、今年は八重山のみに関わらず宮古島地域でもオニヒトデが大発生しています。
サンゴの保護活動で発生する駆除したオニヒトデについて、有機肥料として有効活動をして行きたいと思っていますので、漁業協同組合、ダイビング協会などの方は弊社にご連絡をお願いします。
有限会社シンソー
TEL:098-964-1148
担当者:與那嶺(よなみね)
以下、琉球新報社の新聞記事を掲載
ボランティア、駆除限界 八重山でオニヒトデ大量発生
2009年2月13日 【石垣・竹富】 琉球新報ニュース
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-140747-storytopic-1.html
国内最大のサンゴ礁が広がる石西礁湖や、国内一の人気ダイビングエリアとして知られる石垣島など八重山海域で、2008年のオニヒトデ駆除数が6万5392匹で昨年(3358匹)の19.5倍にも上り、サンゴの天敵オニヒトデが大量発生していることが八重山ダイビング協会(84社、園田真会長)のまとめで分かった。
同協会環境対策委員の佐伯信雄さんは「座間味島や恩納村などの周辺は減少傾向だが、八重山は急激な増加を示しており、今年は危機的状況も予想される」と警戒している。
八重山海域では1970年から80年にかけてオニヒトデが大量発生し、81年には51万5750匹を駆除。当時、ほとんどの海域でサンゴが壊滅状態になった。大量発生の原因は不明だが、同協会は7年前からボランティアでオニヒトデを駆除していた。
08年に入り目撃数が増え、大きさもこれまでの倍近い35―40センチと巨大化、日中にも活発に活動するのが確認された。08年、同協会と竹富町ダイビング組合(21社、宮本守康組合長)が延べ790人を動員し約70日間の駆除活動をしたほか、環境省も駆除事業を行った。特に石垣島北西部の川平石崎や鳩間島と西表島の間の「バラス」周辺に多く、バラスでは6月に1人1タンク当たり(潜水時間約1時間)の駆除数を示す駆除効率が97と驚く数値が出て、大量発生が裏付けられた。
今年、竹富町ダイビング組合は月3回の頻度で駆除予定だが、組合員の曽我勲さんは「組合費で船の燃料代を出してのボランティアは体力的にも金銭的にも厳しい」と悲鳴を上げる。
オニヒトデ、宮古周辺で急増 50メートル四方20個体確認
2009年2月15日 【宮古島】
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-140795-storytopic-5.html
サンゴ礁へ食害をもたらすオニヒトデが宮古島周辺で急増していることが、環境省の2008年度サンゴ礁調査で分かった。池間島北方の広大なサンゴ礁群「八重干瀬」中央付近のカナマラでは、大発生の目安となる1地点10個体の2倍の20個体を確認した。同地点で白化現象も確認され、被害に追い打ちを掛けている。大人数で上陸する八重干瀬観光の形態にも課題を投げ掛けている。
サンゴ礁調査は毎年、環境省が全国各地の専門家へ委託しサンゴの被度や白化などを調査。今回のサンゴ礁調査は08年8月末―12月下旬に実施した。オニヒトデは50メートル四方を1地点とし15分間、目視で個体数を確認した。
調査地点の14カ所のうち(1)八重干瀬のカナマラ(20個体)(2)高野漁港沖の2段干瀬(30個体)(3)池間島北のカギンミ(20個体)―の3カ所でオニヒトデの大量発生を確認した。
八重干瀬は毎年旧暦3月3日の浜下り(サニツ)の時期に海面に浮上し住民や観光客が上陸し散策などを楽しむ。
調査した梶原健次さんは「広い八重干瀬の中でもカナマラの1地点でのみオニヒトデが確認され、他の場所は分からない」と説明。観光形態には「上陸した観光客がオニヒトデを踏んでけがをしたり、サンゴ礁の減少へ拍車を掛ける危険もある。今後は周遊など他の方法を考えて良いのでは」と指摘する。
観光上陸を実施する地元海運会社は「事故が無いよう上陸時に船からサンゴ礁が少ない場所まで橋をかけて対策するので大丈夫。自然も守りながら上陸観光をしたい」と話す。
宮古島観光協会の渡久山明事務局長は「船会社と連携しながらできるだけ安全な場所を選ぶなど対応する」と説明。「これまで実施した(試験的な)周遊観光では上陸に比べ客の満足度が低い。しかし今後はサンゴ礁へ負荷をかけない形を検討していきたい」と強調した。
.

主な内容は、『サンゴを守る活動において駆除した後のオニヒトデを有機肥料の原料として有効活用を目指す』という内容でお話します。
弊社は、2年ほど前からこのオニヒトデについて有効利用できないか検討・準備を進めており、昨年、読谷村漁業協同組合と協力の依頼をしていました。
今回、その考えや取り組み方をラジオで話して欲しいと依頼になり、ゲスト出演する事になりました。
昨年、八重山地域でオニヒトデが大発生し、今年は八重山のみに関わらず宮古島地域でもオニヒトデが大発生しています。
サンゴの保護活動で発生する駆除したオニヒトデについて、有機肥料として有効活動をして行きたいと思っていますので、漁業協同組合、ダイビング協会などの方は弊社にご連絡をお願いします。
有限会社シンソー
TEL:098-964-1148
担当者:與那嶺(よなみね)
以下、琉球新報社の新聞記事を掲載
ボランティア、駆除限界 八重山でオニヒトデ大量発生
2009年2月13日 【石垣・竹富】 琉球新報ニュース
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-140747-storytopic-1.html
国内最大のサンゴ礁が広がる石西礁湖や、国内一の人気ダイビングエリアとして知られる石垣島など八重山海域で、2008年のオニヒトデ駆除数が6万5392匹で昨年(3358匹)の19.5倍にも上り、サンゴの天敵オニヒトデが大量発生していることが八重山ダイビング協会(84社、園田真会長)のまとめで分かった。
同協会環境対策委員の佐伯信雄さんは「座間味島や恩納村などの周辺は減少傾向だが、八重山は急激な増加を示しており、今年は危機的状況も予想される」と警戒している。
八重山海域では1970年から80年にかけてオニヒトデが大量発生し、81年には51万5750匹を駆除。当時、ほとんどの海域でサンゴが壊滅状態になった。大量発生の原因は不明だが、同協会は7年前からボランティアでオニヒトデを駆除していた。
08年に入り目撃数が増え、大きさもこれまでの倍近い35―40センチと巨大化、日中にも活発に活動するのが確認された。08年、同協会と竹富町ダイビング組合(21社、宮本守康組合長)が延べ790人を動員し約70日間の駆除活動をしたほか、環境省も駆除事業を行った。特に石垣島北西部の川平石崎や鳩間島と西表島の間の「バラス」周辺に多く、バラスでは6月に1人1タンク当たり(潜水時間約1時間)の駆除数を示す駆除効率が97と驚く数値が出て、大量発生が裏付けられた。
今年、竹富町ダイビング組合は月3回の頻度で駆除予定だが、組合員の曽我勲さんは「組合費で船の燃料代を出してのボランティアは体力的にも金銭的にも厳しい」と悲鳴を上げる。
オニヒトデ、宮古周辺で急増 50メートル四方20個体確認
2009年2月15日 【宮古島】
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-140795-storytopic-5.html
サンゴ礁へ食害をもたらすオニヒトデが宮古島周辺で急増していることが、環境省の2008年度サンゴ礁調査で分かった。池間島北方の広大なサンゴ礁群「八重干瀬」中央付近のカナマラでは、大発生の目安となる1地点10個体の2倍の20個体を確認した。同地点で白化現象も確認され、被害に追い打ちを掛けている。大人数で上陸する八重干瀬観光の形態にも課題を投げ掛けている。
サンゴ礁調査は毎年、環境省が全国各地の専門家へ委託しサンゴの被度や白化などを調査。今回のサンゴ礁調査は08年8月末―12月下旬に実施した。オニヒトデは50メートル四方を1地点とし15分間、目視で個体数を確認した。
調査地点の14カ所のうち(1)八重干瀬のカナマラ(20個体)(2)高野漁港沖の2段干瀬(30個体)(3)池間島北のカギンミ(20個体)―の3カ所でオニヒトデの大量発生を確認した。
八重干瀬は毎年旧暦3月3日の浜下り(サニツ)の時期に海面に浮上し住民や観光客が上陸し散策などを楽しむ。
調査した梶原健次さんは「広い八重干瀬の中でもカナマラの1地点でのみオニヒトデが確認され、他の場所は分からない」と説明。観光形態には「上陸した観光客がオニヒトデを踏んでけがをしたり、サンゴ礁の減少へ拍車を掛ける危険もある。今後は周遊など他の方法を考えて良いのでは」と指摘する。
観光上陸を実施する地元海運会社は「事故が無いよう上陸時に船からサンゴ礁が少ない場所まで橋をかけて対策するので大丈夫。自然も守りながら上陸観光をしたい」と話す。
宮古島観光協会の渡久山明事務局長は「船会社と連携しながらできるだけ安全な場所を選ぶなど対応する」と説明。「これまで実施した(試験的な)周遊観光では上陸に比べ客の満足度が低い。しかし今後はサンゴ礁へ負荷をかけない形を検討していきたい」と強調した。
.
Posted by シンソーグリーン at 10:39│Comments(2)
│オニヒトデ
この記事へのコメント
私は、以前環境調査の関わる仕事を少しお手伝いしてました。海面と海中にでは、別世界ですよね(珊瑚が痛々しいです)何か手助けしたいですけど、地元に住んでいる以上気持ちしかないですね。。
陰ながら応援してます。でも体には気を付けてください。
( 偶々、検索してたたら、、こちらのブログにきました。)
陰ながら応援してます。でも体には気を付けてください。
( 偶々、検索してたたら、、こちらのブログにきました。)
Posted by kakao at 2009年02月19日 12:14
>kakao様へ
コメント&ご声援有難うございます。
オニヒトデを有機肥料化にする事業は歩き始めたばかりで、実際にはまだ製品化にいたってはおりません。
しかし、この事業は必ず成功させるつもりですので、今後ご声援のほどよろしくお願い申し上げます。
コメント&ご声援有難うございます。
オニヒトデを有機肥料化にする事業は歩き始めたばかりで、実際にはまだ製品化にいたってはおりません。
しかし、この事業は必ず成功させるつもりですので、今後ご声援のほどよろしくお願い申し上げます。
Posted by シンソーグリーン at 2009年02月22日 08:59